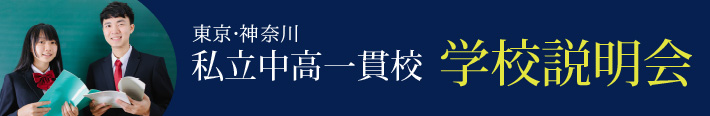青稜中学校・高等学校は、「貢献」「変化」「挑戦」の3つの「C」を重視し、生徒が未来を見据え主体的に学べる環境づくりを推進。教員・保護者と共に成長を支えます。校長先生に青稜中学校・高等学校の特色ある取り組みなど注目ポイント伺いました。
好きなことだから夢中になれる
教科横断型ゼミナール授業

青田校長のゼミでは、菓子メーカーの社員を招き、生徒が「分別しやすいゴミ箱」を発表。(青稜中学校・高等学校)
月曜日の6、7時間目に行われる「ゼミナール」は、最新の社会問題からIT、文学、芸術、運動系まで、教科の枠にとらわれない自由なテーマで14講座を開講しています。
中学2、3年生はその中から興味のある講座を1つ選び、異学年混合のグループワークやディスカッションを交えながら個々の学びを深めていきます。
青田校長も「2030~未来への挑戦~」と題し、「SDGs」をキーワードに未来を良くする方法を考えるゼミを主催。有名企業とコラボレーションし、生徒のアイデアで商品開発を行うこともあるそう。
斬新な取り組みで生徒たちの好奇心を刺激します。

バドミントンのゼミでは、技術に加え、戦略を考える力やコミュニケーション能力も育みます。(青稜中学校・高等学校)

美術のゼミは、好きな画家の技法を学び、自分が描く絵に活かします。(青稜中学校・高等学校)
中1から自然と身につく
「この場所で学ぶ」という意識

「Sラボ」の利用は生徒一人一人が持つタブレットのアプリから予約できます。(青稜中学校・高等学校)
自学自習の習慣を中学のうちから定着させようと導入されたのが「Sラボ」です。
個別ブースがずらりと並ぶ専用ルームには5~10人のチューターが常駐し、生徒一人一人の質問に答えてくれるほか、学習計画の相談も可能です。
「家に帰ったら勉強に集中するのはなかなか難しい。それならすべてを学校のなかで完結できる環境をつくろうと考えました」と青田校長。
定期テスト前に限らず、放課後の空き時間や、夏休み期間中など、全校生徒の約7割が自主的にSラボを利用しているそう。
こうした環境も確実に学力アップにつながっています。


図書室内や職員室横に設置された通称「白テーブル」でも、自習する生徒の姿が多数見られます。どこで何をするかを自分で決められる自由さも青稜の魅力のひとつです。(青稜中学校・高等学校)
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます