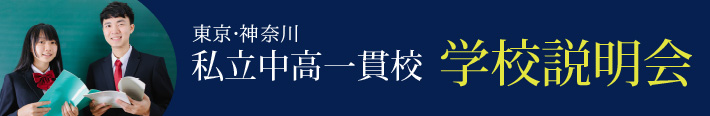創立以来、「真・善・美・聖・健・富」をバランス良く育む「全人教育」を行ってきた玉川学園中学部・高等部。小学部から高等部までをひとつの学校として捉えた独自の一貫教育プログラム「K-12」を導入し、生徒一人一人の適性に合わせた豊富なカリキュラムを実践しています。
中でも学園を象徴する教育、「自由研究」を取材しました。
自学自律の精神のもと、とことん興味を探究する自由研究

木工をテーマにした自由研究でバイオリンを制作。写真の生徒はオーケストラに所属しており、「手作りのバイオリンを完成させてオーケストラで実際に演奏すること」を目指しているようです(玉川学園中学部・高等部)
一般的に「自由研究」というと夏休みなどの長期休暇期間に取り組む短期的な学びがイメージされますが、玉川学園の「自由研究」は、伝統的に授業として行っている主体性に特化した学びを意味します。
中学1年・中学2年では教科発展型の全17分野から、それぞれが興味のあるテーマを選択し、毎週2時間という授業時間を活用して、とことん研究に取り組みます。
テーマは国語・数学・英語・理科・社会にとどまらず芸術や音楽・スポーツまで幅広いことが特長で、3Dプリンターを使った研究やレーザー加工機による木工制作、咸宜園で行われる茶道など、充実した施設環境をもつ同校ならではのテーマも多数あります。

美術の自由研究では、大きなキャンバスに油絵を描く生徒もいれば、水彩画やコンテを使った作品を制作中の生徒も。完成した作品は、3月に開催される「玉川学園展ペガサス祭」で展示されます(玉川学園中学部・高等部)
サンゴの研究を選択したある生徒は、中学1年のとき、「なぜサンゴ礁に魚が集まるのか」をテーマにして、サンゴと魚、それぞれが受けるメリットを調べ、レポートにまとめて発表しました。
中学2年では、「株となるサンゴの切り方で生育は変わるのか」を研究。学内の水槽では沖縄のサンゴの株を分けてもらい、増やすために飼育しているのですが、その際の株の切り方が棒状の長いものとごく小さく切ったものでは、その後の成長度合いにどのような差が出るのかを調べた、といいます。
このようにわずか1年間でより深いテーマや研究内容にたどり着く生徒も多く、SSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)の大会や学会で成果を発表する意欲的な生徒も少なくありません。
中3でさらに発展する探究学習、論文とプレゼンスキルの向上を目指す
中学3年では問いの立て方から情報収集、論文の書き方、発表の仕方、最終的な評価や振り返りまで、本格的な探究活動のスキルを学びます。
高等部ではさらに大学での研究や将来の進路を意識した取り組みへとつなげます。

書道では、草書体の「遊」という漢字にチャレンジ。普段は見慣れない文字のため苦戦する生徒に、先生が「折りたたんで広げた半紙の折り目をガイドにバランスを調整して」とアドバイス。何度か繰り返すうちにコツをつかみ、見事な作品が次々と生まれていました(玉川学園中学部・高等部)
「自由研究などの探究的な学習を通して、高等部に上がるころには、深みと丸みに加えて、究みのある人間へと成長してほしい」と中西先生。
「AIなどの進化は目を見張るものがありますが、最後は人だと考えています。単なる詰め込み型の勉強をした生徒より、主体的で探究的な学びをコツコツとやり続けた生徒のほうが最後には必ず伸びると信じています」。
ひとつの研究に6年間特化した生徒の中には、進路先の大学を「自分の研究が続けられそうな研究室があるから」との理由で選んだ子もいるそう。
未来にこそ花開く探究型の学びは、これからも玉川学園の象徴として続いていきます。

手芸の自由研究では、ミシンに向かい手提げバッグを制作。これをベースに、刺繍やビーズ、編んだ毛糸など、思い思いの装飾を加えてオリジナルの作品を完成させます。細かな作業に「難しい!」との声も聞かれましたが、ていねいに作業に取り組んでいました(玉川学園中学部・高等部)

化学室では「水面に文字を書くには?」をテーマに実験が進行中。生徒たちから出た案をひとつひとつ試していき、どれが正解かを確かめます。「次こそ文字が浮かぶのでは?」と、みんな水面に釘づけ、興味津々で実験を見つめる生徒たちの姿が印象的でした(玉川学園中学部・高等部)
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます