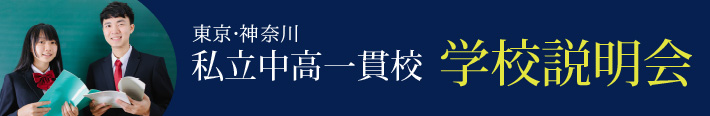東急大井町線、JR京浜東北線、東京臨海高速鉄道りんかい線の3路線が乗り入れる大井町駅から徒歩7分。
駅前の喧騒から一転、公園が点在するのんびりとした街並に佇む青稜中学校・高等学校は、1995年の男女共学化以降、大胆かつスピード感のある教育改革を進めています。
「社会に貢献できる人間の育成」を掲げる同校の広報部長 谷田貴之先生に、特長ある学び「ゼミナール」についてお話を伺いました。
多種多様な「ゼミ」で好奇心の扉を開く

青稜中学校・高等学校のSDGsの課題に取り組む青田校長ゼミ(青稜中学校・高等学校)
中学では「おもしろさや楽しさとの出会い」をテーマに、先生たちが工夫をこらした授業を行なっています。
中学2年、中学3年を対象とした特別授業「ゼミナール」もその中のひとつ。まさに大学の「ゼミ」のような内容の講座を用意し、生徒一人ひとりの学ぶ意欲や興味を引き出しています。
SDGsの問題解決がテーマのゼミや、気象予報講座、物語の読解力を高めるゼミなど、バラエティ豊かな13〜14講座が毎年開講されています。
青田校長による「2030〜未来への挑戦〜」では、はじめに持続可能な17の開発目標の基礎知識を学習。その後、実際に企業を招き、企業が取り組んでいるSDGsを学びます。
そして、班に分かれてグループディスカッションを行い、解決策を考えて発表します。1年の間に3社ほどが来校しますが、すべての企業とのディスカッションを終えた後、最終的には自分なりのSDGsを考えて問題解決に取り組みます。
昨年は、ごみ問題の解決に向けて分別したくなるごみ箱を考えましたが、実際に生徒が考案したそのごみ箱が今年の秋に校内に設置される予定です。

企業が抱えるSDGsの課題に取り組む青田校長のゼミ「2030〜未来への挑戦〜」。毎年、江崎グリコやサントリー、花王など、数々の企業が学校を訪れ、生徒と一緒に課題に向き合います。(青稜中学校・高等学校)
青田校長が一番初めのゼミで取り組んだテーマは脱炭素でした。
CO2を排出しないクリーンエネルギーのひとつ・太陽光を使ったグリーン100%の電力を提供する「しろくま電力株式会社」に協力してもらい、青稜で脱炭素に関する講義を開催。太陽光発電所見学などを行い、生徒たちの理解を深めました。
そして、青稜のSDGs部が脱炭素社会実現のためのアクションプランを考え保護者会で発表。「ぱわーくん応援金」と題されたこのプランは、家庭の電力を「しろくま電力」にスイッチすると学校側から応援金がキャッシュバックされるというもの。
このプランは実現され、生徒だけではなく保護者も脱炭素を考える良い機会となりました。
先生の得意分野や興味・関心が出発点

自ら現場に足を運び、地域によって千差万別の気象現象について熱弁を奮う理科の松村先生のゼミ「目指せ!お天気お姉さん(お兄さん)」(青稜中学校・高等学校)
他にも、様々な個性豊かなゼミが揃っています。ユニークな点は、ゼミの内容は先生たちの興味や趣味から発案されているところです。
「目指せ!お天気お姉さん(お兄さん)」では、気象予報士になりたかった先生が発案。
実際に先生が積乱雲の発生を予測し、ゲリラ豪雨が起きそうな地点に出向き、雲が湧きはじめるところや、雷が落ちる瞬間、土砂降りになっていく様子を、先生が撮影した映像を見ながら専門的な知識とともに詳しく解説します。
雷を追いかける先生の情熱的な講義に、生徒たちも興味深く耳を傾けていました。

谷田先生のゼミ「多様なメディアによる物語を読み解く〜絵巻からアニメ・映画へ〜」では、iPadを使ってマンガやアニメを作ります。生徒からもっとアニメ制作を学びたいとの声があがり、ゼミから派生したアニメーション部もできました。(青稜中学校・高等学校)
谷田先生の「多様なメディアによる物語を読み解く〜絵巻からアニメ・映画へ〜」は、物語の読解力を高めることが目的のゼミで、マンガやアニメ、写真や絵画など、視覚情報から物語を読み解く手法を学んでいく講座です。
「例えば、人物が写っている1枚の写真から、人物像を想定できるようになると、物語や現代文に挿入されている写真やイラストから情報が読み取れるようになるので、文章読解の質が向上していきます」と谷田先生。
取材日は、並べられた3枚のイラストから、文脈を感じ取ることができるかという授業で、擬音語だけで3コママンガを作る取り組みが行われていました。
視覚情報のみから感じ取った擬音を、生徒たちは思い思いにiPadに書き記していきます。

「ダーツ」のゼミでは、ダーツでの心のあり方を日常生活に取り入れることが目標。強いメンタルを保つ方法は普段の生活にも活かせます。(青稜中学校・高等学校)
今年から新設された「ダーツ」は、単にダーツのスキルを高めるだけではありません。
近年、スポーツ競技としてU18の大会が開催されるようになるなど、注目を集めるダーツですが、実は裏テーマとして、ダーツでスポーツ心理学を学ぶ目的もあります。
ダーツは投げ方さえ習得してしまえば、10回中10回同じ所に投げることが可能な競技ですが、それを難しくさせているのは心の問題。心を強くするにはどうしたらよいか学べば、普段の生活にも取り入れることができます。
呼吸法や失敗との向き合い方まで学びます。
今回紹介したゼミのほか、「プログラムを作ろう」や「あみぐるみを作ろう」、「美術ゼミ」など、さまざまな分野のゼミが用意されています。
「『ゼミナール』で、生徒たちは学ぶ意欲や好奇心を高めていきます。そして、自分の中にある興味を知り、将来どんな勉強をしていきたいのか、どんな職業に就きたいのかという、自分の内面を深く考えるきっかけのひとつになっているのです」と谷田先生。
同時に、大人になっても「好き」を追求する先生方の姿勢から、生徒たちは大切なことを学んでいるようです。
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます