「子ども主体の授業」を体感する一日、公開授業研究会を開催

成城学園初等学校と授業てらすが共催した公開授業研究会が開催されました。研究会では、全国から集まった教師たちが、現場の授業を生で観察し、対話を通じて学びを深めました。
今回のテーマは 「子ども主体の授業創造」。教育現場で今、求められているのは「子どもが自ら学び、問いを持ち、友達と学び合う授業」です。それを実現するための授業が、社会・国語・算数の各教科で展開されました。
【社会科授業】教師の“布石”が、子どもの学びを深める

社会科の授業では、筑波大学附属小学校の由井薗健先生が 「子どもが考え続ける仕掛け」 を随所にちりばめた授業を展開。「布石の連続で、子どもの学びが深まる様子に感動した」という声が多数寄せられました。子どもが「自分ごと」として課題に向き合い、意見を交わしながら学びを深める授業は、まさに「子ども主体」の理想形でした。
【国語の授業】対話が生まれる
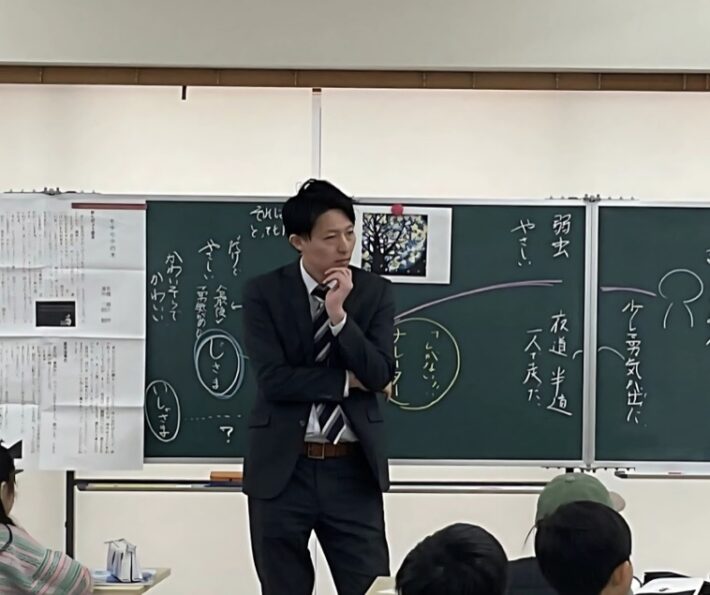
新潟大学附属新潟小学校の中野裕己先生の国語の授業では、「見とり」の重要性が強調されました。子どもたちの反応を的確にとらえながら進められる授業に、参加者からは 「確固たる理論に基づいた実践で勉強になった」「発問の仕方でこんなにも子どもの意見が変わるのか」 という驚きの声が上がりました。
【算数の授業】数学的思考を育む
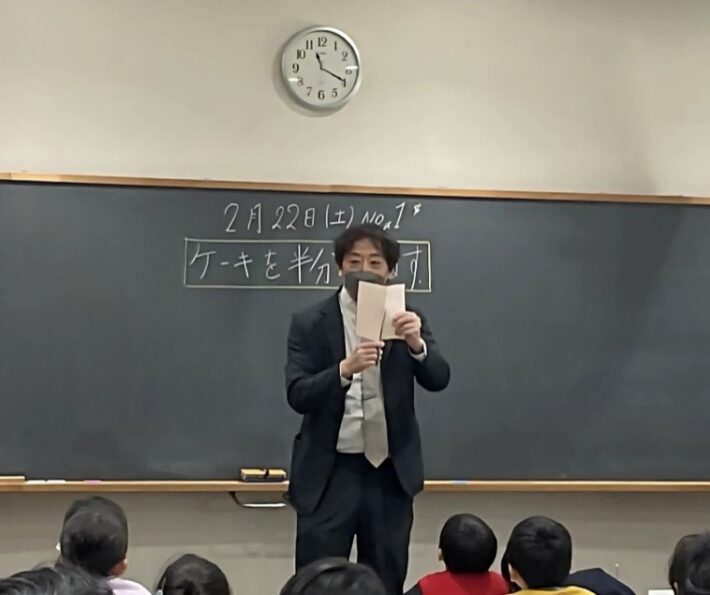
新潟市立上所小学校の志田倫明先生による算数の授業では、子どもたちが自ら問いを立て、解決の道筋を探る様子が印象的でした。「子どもたちが学びたくなる流れが型として示され、大変勉強になった」 という声もあり、授業設計の奥深さを感じた参加者が多かったようです。
■「授業てらす」とは
授業てらすは、全国の教師が学び合い、授業力を高めるためのプラットフォームです。「授業がうまくなることで、子どもと先生がHAPPYになる」という理念のもと、今後も多様な学びの場を提供しています。
授業てらすは、全国の教師が学び合い、授業力を高めるためのプラットフォームです。「授業がうまくなることで、子どもと先生がHAPPYになる」という理念のもと、今後も多様な学びの場を提供しています。



