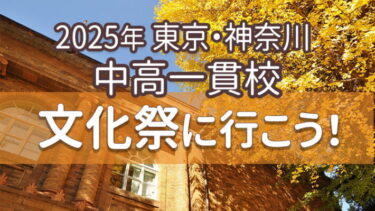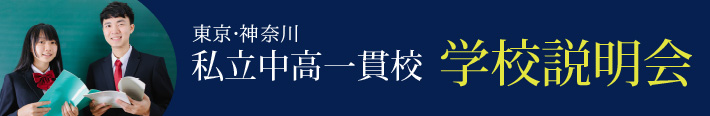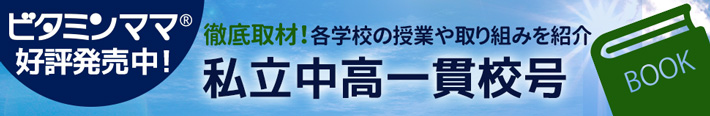一般的には、塾でも通信教材でも「カリキュラム通りに進めるのが理想」と言われます。わが家が利用している中学受験大手塾の通信教材でも、ホームページに学習予定表が公開されており、そのスケジュールに合わせて週テストが毎週末マイページに配信されます。
これまでは「可能な限りスケジュール通りに進めなければ」と思っていましたが、最近は少し考えが変わりました。多少遅れていても、むしろその遅れから得られるメリットもあるのではないかと思うようになったのです。
ビタミンママでは、中学受験ママの奮闘ブログ「一輝一憂」で、中学体験記を書いてくれるママライターを募集しています。皆様の現役・過去の体験談をビタママONLINEで発信してみませんか?詳しくはこちらをご覧ください!
スケジュールの遅れを取り戻した夏休み
ヒラメが通信教材を始めてからは、予定より遅れるたびに「大丈夫かな」と気をもんでいました。本人のペースを尊重したいと思いつつも、スケジュール表を見ては、つい焦ってしまう自分がいました。

そんな中で迎えた今年の夏休み。時間に余裕があったこともあり、予定に追いつくことができました。最終的に、長く続いていた遅れを解消し、夏休み明けの公開組分けテストでは、久しぶりにスケジュール通りに学習を終え、マイページに答案をアップロードして提出することができました。
私立中高一貫校では、秋の文化祭シーズンが始まりました! 文化祭は、学校の中の様子や雰囲気がわかり、実際に通っている生徒との交流や受験相談まで、各学校の特色を知る絶好の機会です。 9月~11月に開催される、東京・神奈川エリアの注目[…]
オンタイムより効率的?遅れることのメリット
公開組分けテストをオンタイムで受けられた達成感はありましたが、結果と解答が見られるのは数日後。全体の採点と集計を経てからの公開なので、それまでは解き直しができません。
一方、スケジュールから少し遅れて受けた場合は、マイページでの受付は締め切られているため、自己採点するしかありません。けれども、すでに解答と解説が公開されているので、テストを解き終えたその場で丸付けし、間違えたところをすぐに見直すことができます。
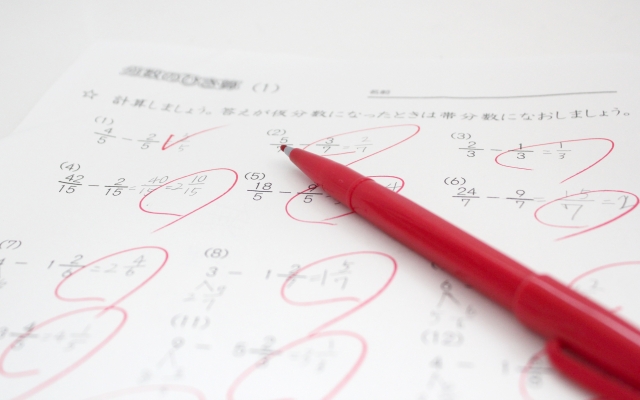
この「すぐ直せる」タイミングのよさは想像以上に大きく、頭の中に問題の記憶が鮮明に残っているうちに解き直せるため、理解の定着が早いのです。
数日経ってからだと、「この問題どんな内容だったっけ?」「どう考えたんだっけ?」と記憶をたぐるところから始めることになり、効率が落ちてしまいます。さらに、時間が経つほど解き直しそのものが億劫になってしまう面もあります。
もちろん、自己採点である以上、特に国語の記述などは塾の採点基準とはズレが生じ、正式な提出時とは偏差値が異なるというデメリットもあります。
それでも私は、解き終わったその場で間違いを確認できる点で、「遅れて受けるメリット」は大きいと感じています。
「スケジュール通り」にとらわれすぎない学び方
とはいえ、どんどん遅れてもいいという話ではありませんし、「のんびりやればいい」と言いたいわけでもありません。マイページの機能や採点方法など、用意されている仕組みをどう活用するかは、それぞれの家庭や子どもの学習スタイル次第だと思っています。
もしヒラメがオンタイムで提出し、正確な順位や偏差値を知ることでモチベーションが上がるなら、それはそれでいい。一方で、スケジュール通りに進めることにとらわれすぎず、今のヒラメにとって一番やりやすい形で仕組みを使っていくことも、通信教材の大きな利点だと思います。
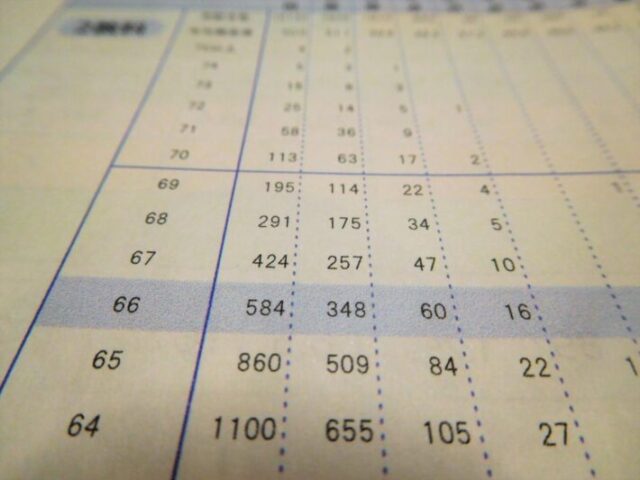
わが家では今、だいたい1〜2週間遅れくらいのペースで進めています。その分、テスト直後にすぐ見直しができ、理解の抜けをその場で確認できます。そんな“遅れの中にあるメリット”を感じながら、無理のないペースで進めていけたらと思っています。
続きを読みたい方はここをブックマーク!過去記事から最新記事まで一挙公開中です!