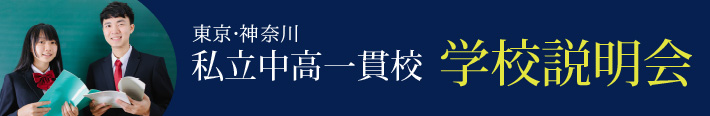日本女子大学附属中学校・高等学校では、「自学自動」の精神のもと、本物に触れる教育を重視。理科実験や生活に根ざした学びを通じて主体的に疑問を解決し、高度な学びにも挑戦。自治活動や体験学習を通じ、社会で活躍する力を養います。広報部主任 森田 真 先生に日本女子大学附属中学校・高等学校の特色ある取り組みなど注目ポイント伺いました。
豊かな周辺環境を生かし
実体験重視の教育を実践

学校周辺には観察対象となる植物や生物がいっぱい! (日本女子大学附属中学校・高等学校)
「森の中の学校」の異名をもつ同校では、多摩丘陵の里山に囲まれた自然豊かな環境を生かし、さまざまな取り組みを行っています。
中1美術の「わたしの木」では、自分が気に入った木のスケッチを通して、“自分と向き合う”経験をします。このスケッチをもとに、100回以上も色を重ねる版画作品に取り組みます。
理科では、校地内を散策し、自生する花などの観察を行います。採取した花は分解して押し花にし、その構造を調べてプリントを作成。
また、広大な敷地内のさまざまな地形を利用して、班別で各地点の風力や気圧、湿度などの観測も行います。

スケッチ中は私語厳禁。静かに自分と向き合います。(日本女子大学附属中学校・高等学校)

「わたしの木」の版画制作に取り組む事前学習として、落ち葉を利用したステンシルに挑戦。補色や色の混合といった美術知識を学びつつ、美的感性を伸ばします。(日本女子大学附属中学校・高等学校)
情報教育の土台を作る
中学「技術・家庭科」の取り組み

AIを活用して「じゃんけんゲーム」を作る取り組みでは、授業以外の時間を使って熱中する生徒も。(日本女子大学附属中学校・高等学校)
中学の「技術・家庭科」ではプログラミングを中心とした情報教育を実施。
情報・テクノロジー教育を先導するNPO団体をアドバイザーに迎え、AIアプリケーションを使用したゲーム制作やプログラミングソフトでの初歩的なコーディングに取り組みます。
希望者には3Dプリンターを使った制作を行う講座を実施するなど、高校から教科化される「情報」の授業へとつなげます。
「中学は本格的な情報教育への土台作り。授業を重ねるごとにプログラミングの楽しさに目覚める生徒が多く、今後はIT分野への進路選択などにもつなげていきたいと考えています」と森田先生。

冬季休暇を利用した「プログラミング講座」では3Dプリンターを使用し、立体地図の制作などを行いました。(日本女子大学附属中学校・高等学校)

1人1台のタブレット端末で、お互いの意見や考えを共有。(日本女子大学附属中学校・高等学校)
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます