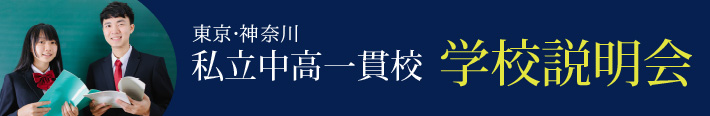横浜女学院中学校高等学校は、「愛と誠」を校訓にキリスト教精神を軸とした教育を実践。探究活動やESD授業を通じ「6領域12コンピテンシー」を育成し、地域から世界へ貢献する人材を目指します。教務部長・社会科主任鈴木 俊典 先生に横浜女学院中学校高等学校の特色ある取り組みなど注目ポイント伺いました。
「鳴子スタディツアー」で知る
未来につながる社会の取り組み

チェーンソーを使用し、全員が伐採を体験します。(右下)東北大学では講義を受講。(横浜女学院中学校高等学校)
高1の「鳴子スタディツアー」では、校内の机やイスに使用されている鳴子の木材を扱う林業従事者のもとを訪ね、木材を取り巻く社会問題や現状を学びます。
外国産の安価な木材輸入を辞めて森林保護活動に従事されている方の体験談を聞き、伐採体験や端材を家具やチップなどに有効活用する取り組みを見学。
また、東北大学の川渡フィールドセンターを訪れ、大学の先生に講義をしていただき、生ゴミからメタンガスを発生させる「エネルギーの循環」についても学びます。
最新の大学研究施設の見学や女性研究員の活躍についての講演を聞く機会もあり、文理選択に向けて、将来を考えるきっかけにもなるそう。

事後学習として、鳴子の地域活性をテーマに東北大学が募集する「アントレプレナーシップ」に参加します。2023年度は、応募した2組のグループが最優秀賞、優秀賞を受賞!(横浜女学院中学校高等学校)
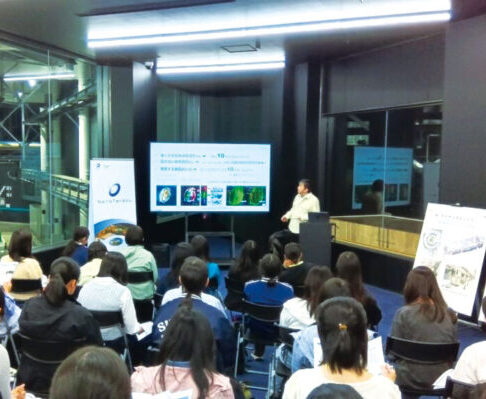
東北大学では講義を受講。(横浜女学院中学校高等学校)
「成功体験」を生徒全員で共有
行動を起こすモチベーションに

高1の生徒は短期留学で感じた「日本とアメリカの違い」について英語を交えてプレゼンテーション。(横浜女学院中学校高等学校)
月に1、2回実施される全校集会「Assembly」は、自分のチャレンジを全校生徒と共有する取り組みです。
登壇者は、自ら発表を希望した生徒で、テーマも発表の仕方も生徒が決定。学内外を問わず何かに挑戦してみようという姿勢を引き出します。
「先日発表した高2の生徒は、慶応義塾大学主催の小論文コンテストに参加したことを報告してくれました。
受賞には結びつかなかったけれど、6000字以上の小論文を仕上げることができたことに大きな達成感を感じたそうです。
挑戦体験や自分なりの成功体験を語ってくれる生徒に触発されて、たくさんの挑戦をしてほしいと考えています」と鈴木先生。

生徒の学外の成果は校内での展示も。(横浜女学院中学校高等学校)

司会進行も務める生徒会は、授業で受けた「リーダー講習会」の内容を、SDGsや日本のジェンダーギャップの問題に絡めて発表。(横浜女学院中学校高等学校)
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます