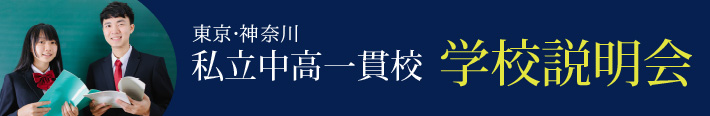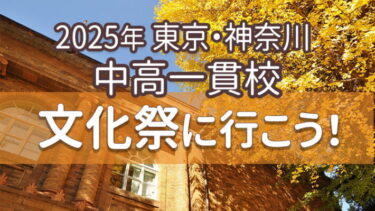成城学園前駅から徒歩10分あまり、都内屈指の豊かな環境の住宅街の先に“トシコー”の愛称で知られる東京都市大学付属中学校・高等学校はあります。
建学以来、次代を担う、創造力と行動力に富んだ若者を育て、社会でリーダーシップを発揮できる人材を送り出してきました。
進学校として名高い同校は、体育の授業にも主体的な学びの機会を求めています。広報部主任の田中 望先生にお話を伺いました。
フラッグフットボール “考える体育”の実践
同校の授業では学年が上がるにつれて、志望進路に合わせてより専門的で深い学びを追求し、万全の受験対策を敷いています。
しかし、同校では美術や体育など、ほとんどの生徒の大学受験には必要のない科目にもしっかりと意義を持たせて取り組ませています。
その中でも体育には特徴があります。
学年ごとに多くの時間数を割く種目が1種目ずつあり、中学一年ではフラッグフットボールに20時間程度を割いています。

フィールドを駆け抜けるランプレーはプレーの基本であり花形。身体能力の底上げにももちろん有効です。(東京都市大学付属中学校・高等学校)
あまり聞きなれない同種目は、簡単にいうと身体的接触の少ないアメリカンフットボール。腰につけたフラッグを取ることをタックルに替え、5対5のチーム戦で行うものです。
2028年のロサンゼルス五輪の正式種目にも採用されているほか、高い安全性から小中学校の授業にも取り入れられています。
保健体育教諭の田中先生は「以前から“考える体育”を標榜しており、フラッグフットボールも少なくとも15年以上前から、中学1年の単元で実施しています。なぜ中学1年か。それは、この競技は生徒が主導するチームビルディングの競技だからです」と語ります。
考え、実践する体育が生徒の感性を刺激する
フラッグフットボールでは、アメフトとは違い激しいコンタクトプレーはありません。
「オフェンスはランプレーやパスプレーを組み合わせ、タッチダウンを目指します。
ディフェンスもまた、その作戦を止めるため様々な工夫をし、攻撃側の前進を防ごうとします」というように高度な戦略が絡み合う、知的ゲームでもあるのです。
勝利のためには、ボールを遠くに投げる、足が速い、戦略を立案する、相手のプレーを分析するなどの個々の強みを活かし、一つにまとめ上げていく作業が不可欠です。
「例えば、足の遅い子はチームに不要かというと、答えはノーです。走るより速く効率的に前進できるパスが上手かもしれないし、タッチダウンに向けた作戦立案が得意かもしれない。
あるいは相手の裏をかく洞察力に優れているかもしれない。個々の長所を組み合わせて、勝利という1つの目的に向かう、そのために自分ができることを最大限表現することは現代社会で必要不可欠な能力でもあります」。

プレーは攻守が完全に入れ替わる、野球のような形で進みます。各プレーの前には、必ずチームで話し合いが行われます。(東京都市大学付属中学校・高等学校)
プレー中の生徒に目を向けると、体の大きさも走る速さももちろんバラバラ。
しかしそれぞれ、自分に課せられた役割を全うしようとしているようです。
田中先生も「入学から3カ月、ようやくチームとして形になりはじめた感じでしょうか。これからもっとレベルアップを目指してもらいます」とにこやかに語ります。
「スポーツでは必ず勝者と敗者が生まれます。ある意味、全力を尽くした上での負けを許す必要があります。もちろん勝つことを目的にはしますが、永遠に勝ち続けられるわけではなく、敗北から学ぶこともとても多い。負け方を学ぶこともまた、スポーツではとても大切なことです」と田中先生。
体を動かす中で、勝利への筋道の立て方はもちろん、自然に他者への尊重やルールを遵守するマインドを学んでいくようです。

特徴的な楕円形のボールは、大人でも正確に投げるのは難しいもの。しかし多くの生徒がキレイな回転のかかった投げ方を習得しています。(東京都市大学付属中学校・高等学校)

美しい人工芝のグラウンド。メンテナンスも比較的楽で天候にも左右されにくい、怪我をしにくいことなど土のグラウンドにはないメリットが多数あります。(東京都市大学付属中学校・高等学校)
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます