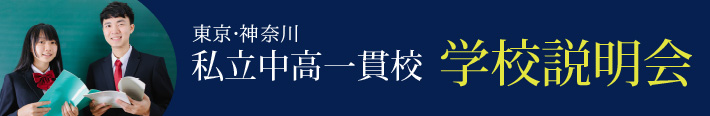異国情緒あふれる山手の丘陵地で、高層ビルが立ち並ぶ横浜みなとみらい地区を見下ろし、心地よい風が吹き抜ける「横浜女学院中学校 高等学校」。
太平洋戦争の戦禍からの再興のため、金子正先生が横浜千歳女子商業学校(創立1886年)と神奈川女子商業学校(創立1943年)を、1947年に合併創立したことで誕生しました。
世界中の多様なトピックをテーマに、新しい世界観や価値観を英語で学び、考える「CLIL(クリル)」の授業を見学し、英語科主任・国際教育主任の鯉渕 健太郎 先生にお話を伺いました。
英語を「読む・書く・聞く・話す」に、「考える」をプラス
中学1・2年で英語を基礎から徹底的に学習する「国際教養クラス」。入学当初はおぼつかなかった英会話も、コミュニケーションツールとなるよう段階を踏んで修得します。
中学3年生~高校2年生で行う「CLIL」の授業は、英語を使いながら学ぶ体験的な学習です。中高の6年間で学ぶ英語4技能(読む・書く・聞く・話す)に、英語で「考える」ことを加えた5技能を磨く特長ある教科で、留学や海外大学進学へ踏み出す後押しにもなっているようです。
見学したのは、高校2年のクラス。1学期のテーマの「世界平和」から、今回は「構造的暴力」を題材に、1人3分ほどのスピーチを行っていました。「構造的暴力」とは、社会の不平等な構造などによって間接的に不利益を被るような状態を指します。生徒たちは国内の教育や医療の格差、ジェンダー問題など、目には見えないけれど身近にひそむ「構造的暴力」について、それぞれの視点で紹介していました。身振り手振りも交えながら、臆することなく流ちょうに発表する姿がとても印象的でした。
 日本語でも難しいテーマ「構造的暴力」について、生徒一人一人が身近にひそむさまざまな社会の不平等を取り上げて英語でスピーチ。(横浜女学院中学校 高等学校)
日本語でも難しいテーマ「構造的暴力」について、生徒一人一人が身近にひそむさまざまな社会の不平等を取り上げて英語でスピーチ。(横浜女学院中学校 高等学校)
幅広いテーマの国際教養を「英語で学ぶ」
ネイティブ教員と日本人教員がペアになって授業を展開する「CLIL」。 担当する鯉渕先生に授業内容について伺うと、「基本は英語で進めますが、オールイングリッシュの英会話と異なり、ときには日本語でディスカッションを行うこともあります。
国際教養の知識として、高校生にとって興味・関心のある話題を取り上げながら、国際的な視点も養うために、英語の文献や留学生の意見なども取り入れています」とのこと。

生徒がペアになってスピーチの練習。ときには海外からの留学生を交えてディスカッションを行うこともあり、多様な価値観にふれながら、英語を介して新たな気づきが得られます。(横浜女学院中学校 高等学校)
例えば今年の高校2年生は、「世界平和」をテーマに、スウェーデンとニュージーランドの留学生を交えて「世界平和度指数ランキング」を題材に意見を交わしたり、世界史の先生とともに平和な時代が続いた古代ローマの政治的背景について学ぶこともあったそう。
「幸福」がテーマの2学期は、聖書科の先生とともに聖書を読んだり、心理学の研究を取り上げたり、お金と幸せについてディベートをしたりと、さまざまな切り口で展開されるそうです。
「英語の上達は、使いながら学ぶことの繰り返しです。英語学習の下地が、ある程度備わっている学年だからこそ、臆することなく英語で話す経験を積み重ねてほしいです」と鯉渕先生。
多角的に考える力を養うことが、本当の教育につながる
横浜女学院中学校高等学校の生徒たちにとって、英語の環境に身を置く大きな経験となるのは、中学3年生の全生徒が参加する「ニュージーランド海外セミナー」です。
国際教養クラスの生徒は約1カ月間現地で過ごしますが、「CLIL」の授業では、その前後にニュージーランドの先住民であるマオリ族との共生や、生物多様性の現状などについて学びます。

中学3年生の生徒が参加する「ニュージーランド海外セミナー」。
国際教養クラスは約1カ月間、アカデミークラスは約2週間、ホームステイを含めてさまざまな経験をします。(横浜女学院中学校 高等学校)
また、高校1・2年生の希望者を対象に行われる同校オリジナルの「スタディツアー」に、2025年度新たに、ブータンが加わりました。 「高校2年で取り上げるテーマの『幸福』とも関連しますが、ブータンはかつて『世界一幸せな国』と呼ばれていました。幸福の感じ方はいろいろな側面を持ち、時代によっても変化します。授業ではスタディツアーで見聞きした今のブータンの様子も紹介し、考えを深める予定です。同じく高校2年生では広島で平和学習を行うので、授業ではアメリカ人教師とともに、日本とアメリカの歴史教科書を読み比べて、どのように書かれているか比較していきます。事実は一つでも、立場が違うと捉え方が違う。多角的に考える力を養うことが、本当の教育につながると思います」(鯉渕先生)
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます