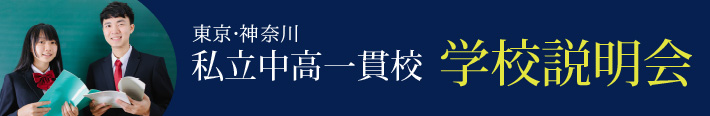明治期の政治家、榎本武揚が設立した徳川育英会の育英黌農業科をルーツにもつ東京農業大学の隣に、東京農業大学第一高等学校・中等部があります。
同校の教育理念は「知耕実学」。敷地内に豊かな自然を擁する同校で、生徒はさまざまな実学を通して自らの“知の土壌”を耕し続けています。
美術担当の柳下景子先生にお話を伺いました。
日常とは切り離せない“美術”の世界
夏を目前に控えた午後の授業、生徒たちが各自のICT端末をせわしなく操作しています。
多くの授業でPCやタブレット端末を使うことは当たり前の光景になりましたが、それは美術の授業でも同じ。

先生に指導を受けながら動画制作。先生のアドバイスで、こだわりの作品が生み出されます。(東京農業大学第一高等学校・中等部)
いわゆる絵を描く、造形をするといったファインアートの授業もありますが、中学2年生の美術の授業では自分が生み出したキャラクターを動かすアニメーション制作に取り組んでいるのです。
キャラクター作りに3時間、アニメーション制作に6時間と、かなりの時間をかけます。
「多くの生徒にとって美術は受験科目ではありませんが、この先の人生、美術と無縁に生きていくことはないと考えています。社会に出てからも、自分の思いや考えを視覚的に表現することが必要な場面も多々あります」と担当の柳下先生。

オリジナルキャラクターをどう動かす? 思ったように動かない! アニメーション制作は試行錯誤の連続です。(東京農業大学第一高等学校・中等部)
世の中にあふれるさまざまな表現から、作り手の思いを汲み取ることや、その価値を知ってほしいと言います。
「特に今はICT端末がありますし、デジタル活用することで、美術に苦手意識をもつ生徒もチャレンジしやすく、表現の幅も広がります。アニメが好きという子も多いですし」と言うように、生徒はそれぞれ生き生きとした表情で授業に取り組んでいます。
友だちと制作過程を共有したり、先生と相談したり。ほんの数十秒のショートムービーですが、ビジュアルはもちろん、ストーリーも練られた作品ばかり。
自己表現として、それを他者に伝えるコミュニケーション手段として、確実に深い学びにつながっているようです。
自分の好きなものに向き合う、それを突き詰める
知的好奇心が高い生徒が多いと語る柳下先生。「生徒たちは希望進路に関わらずいろいろなところにアンテナを張れているなと感じます」。
柳下先生は一中一高ゼミでは陶芸を教えています。「もともとやっていたわけではないのですが、校内に陶芸窯があったので自分でも勉強しました」と、自身の探究心もかなりのもの。
「電動ろくろはかなり難しいので手廻しろくろなんですけどね。去年、東大に受かった子は美術部で陶芸に取り組んで『陶芸に向き合ったからこそ受験に向き合えた』とメッセージを残していました」と笑顔を見せます。
「教育の最終目標は自立」と柳下先生。「自分の好きなものに向き合う、それを突き詰めることが、自立につながります」と語る目には力が宿ります。

ラウンジ入り口に鎮座するステゴサウルス。校内にある美術作品やオブジェなどの多くは生徒たちの作品です。(東京農業大学第一高等学校・中等部)
「先日、ある卒業生の舞台を見に行ったんです」とにっこり。芸術系分野を目指す生徒もいるとはいえ、進学校である同校出身者の大多数の人生からすれば、役者という道は“とがった”進路かもしれません。
ですがこれこそが、好きに向き合い、突き詰めた結果。人生にはいろいろな可能性があり、道は無限に広がっていることを体現した教え子を語る姿に、教育者としての喜びがにじみます。
※校名をクリック(タップ)すると詳細ページに飛びます