コロナ禍を受けて、國學院大學の先生方により緊急展開された連載企画「すくすく子育てエッセイ(在宅編)」をお届けします。自宅でテレワークを続けながら子育てに奮闘しているパパママや、お友達とも自由に遊べず寂しい思いをしている子どもたちへの応援メッセージが込められたエッセイです。
子どもたちに「さんま」が無くなった、と言われます。「さんまがない」とは、子ども社会から、「時間、仲間、空間」の三つの間(ま)、つまり時間的余裕、人間関係、そして遊び空間が無くなった、という憂いの言葉です。「さんまがない」は、家庭にとっても同様です。例えば、時間的余裕がなければ、家庭内の親子の会話も、なかなか成立しません。会話が成り立ったとしても、形式的にならざるを得ません。
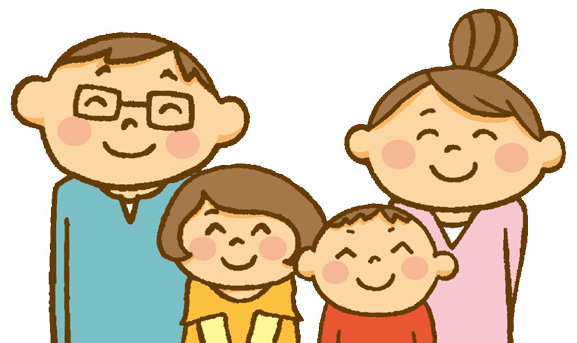
しかし、緊急事態による休校という不幸な形ではありますが、今日、「時間、仲間、空間」の「さんま」が生まれました。親子の会話の「さんま」もできました。 だが、ここでも、「親子の会話と言われても‘ネタ’が無い」という嘆きの声が聞こえてきます。休園、休校中の今、幼稚園、学校の話題が一切無いのですから、それも当然です。そこで今回は、親子会話の大切な材料としての読書を取り上げたいと思います。

児童文学者の椋鳩十さんは、「親子20分間読書運動」を全国に展開しました。椋鳩十さんの動物文学の一つに、『大造じいさんとガン』(ポプラ社、他多数)があります。老狩人と利口なガンの群れの頭領「残雪」との戦いが描かれています。老狩人が残雪を見上げて叫ぶ、「おれたちはまた堂々とたたかおうじゃないか」に込められた彼の気持ちを汲めない時は、単なる戦いの話と読み取るかも知れません。

しかし、親子で話し合った後は、人間と動物とのヒューマンな関係、人間への信頼、人間はすばらしいに、読み取りが変わっていきます。「たたかおうじゃないか」は、「おまえはすごいやつだ」という老狩人の残雪への畏敬の念が込められていることが、わかるのです。
本や絵本は、登場人物や動物の気持ちにならなければ、その読み取りはできません。言い換えれば、「優しさ(思いやり)」が無ければ、読書は困難であり、読解は不可能なのです。今日、子どもたちが、本を読まない、本が読めないというのは、決して国語の力が落ちたからではありません。親世代よりも、今の子どもたちの方が、国語のレベル(国語力)は数段高くなっています。子どもの教科書を一度、のぞいてみてください。
もう一つ、新美南吉さんの『ごん狐』(偕成社、他多数)を挙げてみましょう。

小狐のごんは、自分のいたずらで、兵十が最愛の母親の病気を治す目的で捕まえたウナギを逃がしてしまったことを後悔します。毎日栗や松茸を置いておくようになります。しかし、そんなことはつゆぞ知らない兵十は、ある朝、栗を置くために忍び込んだごんを撃ち殺してしまいます。「ごん、おまえだったのか」。衝撃的なラストです。
この話は動物と人間との伝達の行き違いによる悲劇ということで、国語の授業では一般に、ラストシーンの硝煙の中で「『ごん、おまえだったのか』の後の言葉をつなげなさい」で終わります。しかし、時には教師が脱帽する場合もあります。例えば、子どもたちは、「これは二重の悲劇だ」と言い出すのです。「ごんは、両親がいない。寂しいから仲間を求めていたずらをしていたに違いない。ごんのいたずらのせいで、兵十も母を亡くした。本当は、孤独な者同士で、一番仲良しにならなければならないはずの者が殺し合った。だから、これは『二重の悲劇』だ」
「負けました」。教師も脱帽です。子どもたちが「荒れる」、「やさしさがなくなった」と言われています。しかし、それは先に述べたように、読書など、相手の立場に立って理解する「優しさ(思いやり)」(他者理解)が育たなくなってきたからです。
緊急事態の最中、若者たちの無軌道な「3密」行動が、しばしば報道されました。彼らは、自分の行動が周囲の人々に、いかにコロナ感染という迷惑をかけるかという配慮に欠けているのです。彼らには残念ながら、相手の立場に立って思いやる「優しさ」が不足しているのです。

実は、本が読めないというのは単に読解力の範疇の問題ではなく、今日の子どもたちの情緒面での精神的構造の問題でもあるのです。それ故に、文部科学省も令和の教育改革の一環として、道徳の時間の教科化(「特別の教科道徳」)を図ったのです。
読書、そして幼児の絵本の読み聞かせの中に、子どもたちの心の成長の原点、人格形成のための「心の扉」があります。相手を思いやる「優しさ」が無ければ、本は読めません。また逆に、読書によって、相手のことを思いやる「優しさ」が育つのです。読書や読み聞かせは、知的な創造性ばかりで無く、他者を思いやる「優しさ」も育てます。
休園、休校中の今だからこそ、「読書で一家団らん」は、いかがでしょうか。















